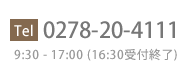梅文湯呑
川喜田半泥子( 1878-1963 )
ほわりとしたのどかな印象の湯呑である。
一筆描きの梅枝と白点の梅花が可愛らしい。
箱には「我れながら 梅え梅え」と書いてあり、「梅(梅絵)」と「上手い(うめえ)」がかけてある。自陶自賛という訳である。
半泥子が作陶で重視したことに「イケコロシ」があるが、これはすなわち「生け殺し」で、芝居における台詞の抑揚・強弱や舞台の進行に合わせた下座音楽の強弱を指す。
半泥子は轆轤を挽くのにもイケコロシが不可欠であると考えた。簡単に言うと、要となる部分だけはゆるがせにしない力をこめ、他は力を抜いておくということのようである。作陶論だが、半泥子の人生論にも思えてくる。
ここで銀座「天一」と川喜田半泥子との関わりについてふれておきたい。
半泥子が初めて「天一」に来店したのは昭和の始め、銀座出店間もない頃のこと※1。初代の矢吹勇雄が自ら集めたうつわの一つ一つが半泥子の目に留まったのがきっかけとなり、半泥子が「天一」に器皿を焼くなど親しく交流した。
ある時には半泥子自ら「天一」の弟子だと言って知人に天ぷらをふるまった。そこまではいいが、乾燥椎茸を水に戻すことも知らずにそのまま供したという※2。何をかいわんや、である。
※1 矢吹勇雄『思いのまま』日経事業出版社、1982、p.187
※2 千早耿一郎『おれはろくろのまわるまま』日本経済新聞社、1988、p.251