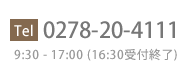層巒山水
池大雅
神童、仙人、奇人、飄逸。池大雅を表す言葉は様々で、幼い頃から異才ぶりを発揮したことが伝えられている。大雅は1723年(享保8年)、京都洛北に池野嘉左衛門の子として生まれた。
7歳で本格的に書を学び、知り合いの僧に連れられて黄檗山万福寺に出向き、僧侶たちに大字を披露したところ、「七歳神童」と絶賛されたことはよく知られている。また、6歳のときに素読(漢文)を学んでいたというから驚きである。
そんな大雅は4歳のときに父を無くし、母と二人で暮らしていた。生活を支えるために15歳頃から京都二条樋口に扇屋を開く。主に中国の版本『八種画譜』に倣った唐絵を扇に即興で描いて売っていた。しかし、当時唐絵はまだ一般に浸透していなかったため、扇はなかなか売れず、遠く美濃、尾張へと行商に行くこともあった。行商の帰り道、売れぬ画扇を竜神へ奉げるのだと川へ投げ込んだこともあったという。
そんな時、一人の武士が大雅の絵に目をつける。彼こそが大和郡山藩の重臣であり、大雅に水墨の技法を教え、パトロンとなった柳沢淇園であった。淇園は指墨(指頭画)の名手であったので、大雅が2、30代の時によく描いた指墨も淇園に学んだと考えられる。大雅は江戸に赴いたときに、指墨を描いて人々を驚嘆させ、その名を広めた。また、1750(寛延3年)、28歳で紀州の祇園南海を訪ね、指墨を披露したところ、即座に才能を認められた。南海は大雅に中国の画譜を与え、文人画を描くように勧めたという。こうした武士階級の初期文人画家が大雅の画業に大きな影響を与え支えとなったのである。
また、大雅は山が好きだった。19歳で知り合った篆刻家の高芙蓉、書家の韓天寿とは生涯の友となり、共に登山に出かけた。「三岳道者」という号を三人で共用していたこともある。大雅は特に20代半ばから30代にかけて、富士山、越中立山、加賀白山、熊野三山、那智山…と思い立つとどこの山へでも旅に出た。妻の玉瀾と暮らした真葛原の家からも東山の景色が見渡せたという。実際に山へ入り、山を見上げ、山を見下ろし、遥か遠くを見渡した経験は山水画の空間表現に大いに役立ったであろう。画論画譜で身に付けた画技は旅での自然観照により、ダイナミックで迫真性の高いものへと発展した。
この作品では、もこもこと丸みを帯びた山々が天高く連なっている。このうねるように脈々と続く山並の表現は『芥子園画伝』等の中国画譜の描き方に類似しており、しっかりとした中国画の学習が根底にあることがわかる。縦長の画面を生かし、高遠法により雄大に描かれた山並は堂々と目の前に聳え立つ。やがて見るものは上へ上へと視線を移動させ、次第に画面の中へと引き込まれ、空高く雲を突き抜けるような感覚にとらわれる。大雅独特の柔和でリズミカルな米点法を用いて、山肌や木に濃淡をつけ奥行きを表現し、さらに余白により大気の流れをも感じさせる構成は見事である。
画譜を参考にしているが、より臨場感と詩情に満ちた作品に仕上がっている。
さてこのように大雅の作風の中心は南宗画であったが、西洋画、北宗画、大和絵、琳派というように古今東西のよいと思った技法はどんどん取り入れた。扇屋として始まった大雅の画業は師弟関係や様式にとらわれることなく自由だったのである。この型にはまらないおおらかさが大雅の作品をスケールの大きいものにしている。
柳沢淇園、祇園南海から受け継がれた日本の文人画は、大雅の好奇心旺盛な活動により独自の輝きを増し、各地へと広まっていった。このあと、玉堂、竹田、文兆と個性的な画家が次々と現れる。
![]() 号・九霞山樵(きゅうかさんしょう)
号・九霞山樵(きゅうかさんしょう)