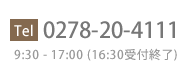手焙り
川喜田半泥子( 1878-1963 )
中を覗くと、僅かに残る灰が見える。
正面と背面には桔梗とおぼしき花を描き、取っ手を側面にぺたりぺたりと貼り付けてある。畳付には達者な筆で「半泥子」の署名がなされている。
「半泥子」の号は、当人が参禅した時の師から授かったものだという。
半ば泥みて半ば泥まず。馬鹿になれ、ものに執らわれるな、泥むなかれ※。泥まみれになりながら轆轤に向かって熱中する半泥子の傍らで、冷徹なほど静かに自分を見つめるもう一人の半泥子がいたのだろうか。
晩年、病に臥せって轆轤を挽けなくなった半泥子は、自作を枕辺に持って来させて慰めにしようとした。しかし、床の間に飾られた木槿や南瓜の花の美しさには遠く及ばないと言って嘆いたという。
半泥子いわく、良いものとは作って作って作りぬいた先にある無心の境地に至って生まれるものである。
それはもはや、泥むとか泥まないといった次元を超えているだろう。半泥子は結局どこまで辿りついたのであろう。庭の花に己の限界を知らされて嘆く半泥子翁。床の間の木槿の美しさは、いっそ残酷であったか。
※藤田等風『定本川喜田半泥子作品集』淡交社、1987、p.7